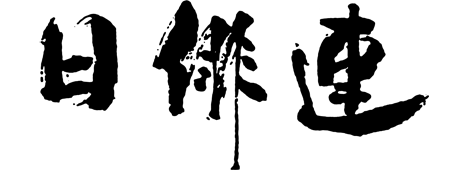目次
-1993年- ノルウェーから二次利用料が
1993(平成5)年3月18日~19日の両日、オーストリアのウィーンでFIA(国際俳優連盟)、FIM(国際音楽家連盟)、IFPI(国際レコード製作者連盟)の三者共催による国際会議が開催されました。「実演家とレコード製作者の権利についての国際会議」と名の付いた会議で、日俳連から江見俊太郎常務理事が参加しました。
「電子機器の発展と普及や衛星放送によって隣国にまで供給されるテレビ番組などについて、実演家やレコード製作者の権利は公正に管理されなければならないが、そのことについてはWIPO(世界知的所有権機関)でも検討中である。いったいどのような結論が導き出されるべきなのか」というのがテーマでした。この検討は、やがて1996(平成8)年の外交会議で採択される「WIPO実演・レコード条約」への討論へと発展していきます。
ただ、今回ここで記録に止めておきたかったのは、この会議中、出席者の江見氏のところにノルウェー俳優ユニオンからもたらされた情報についてです。
同ユニオンの会長で、FIAの副会長でもあるラグニルド・ニガー女史は、会議休憩中のロビーで、江見氏に「日俳連に私たちの組合に委任状を送ってくれるよう手紙を出したのですが、どうなっていますか」と話かけてきたのでした。
「手紙は確かにいただきましたが、意図がよく分からないので、そのままにしてあるのですよ」と応える江見氏にニガー女史が言ったことは「日本で作られた作品がノルウェーで放送されたので、出演者に二次利用料が支払われるのです。だが、ノルウェーにはそのお金を受け取る団体が二つあるので、是非私のユニオンに委任をして欲しい。そうすれば、すぐに日俳連に利用料を送金します」というものだったのです。これは、2001(平成13)年4月、映像の権利者に二次利用料を分配する機構として設立したPRE(映像実演権利者合同機構)と全く同じ形式の組織です。ノルウェーでは、日本に先んずること8年、すでにこうした組織が活動を始めていたのでした。
「俳優の未来を考える会」発進
1980年代後半のバブル経済が崩壊して景気のかげりが顕著になるにつれて、製作会社の中にも資金繰りが行き詰まって倒産したり、倒産までは至らずとも出演者に出演料を支払えないところが散見されるようになってきました。出演料を受け取れなければ、俳優はそのまま生活の危機に脅かされます。しかし、日本の芸能界は古くからの慣習で、明確な書面による契約を結ばないまま口約束だけで出演してしまうのが習わしになってきました。「近代社会では、欧米のような、書面契約を」と口々に唱えながら、いざとなるとそこに至らない現実。この現実を打ち破るためには各方面と団体協約を締結するのが早道ではないか。そんな議論の中から有志が集まって「俳優の未来を考える会」を発進させました。1993(平成5)年1月28日付け「日俳連ニュース」第54号には、担当常務理事として玉川伊佐男氏、高城淳一氏の二人、他に世話人として内田勝正氏、大林丈史氏、小沢象氏、河原崎建三氏、重久剛一氏、中村孝雄氏、浜田晃氏、樋浦勉氏、久富惟晴氏、松山政路氏、宮口二郎氏が名を連ね、次のような発足の挨拶を掲載しています。
そういった日俳連の仕事の大事な点、それをもっと広く知って貰おう、と上の連名の人たちと話し合い、いま表記の「会」で呼びかけ活動を始めることになりました。この会への参加、協力を皆さんに心からお願い致します。
沢山の俳優が日俳連に集まり、舞台、映像、全ての製作会社と団体協約を結び、しっかり出演基盤を固めて仕事に励む、そういう方向に皆さんの力でこの会をもり立てていきたいと考えています」
そして、この未来の会は早速、出演料未払いに関するアンケートを実施しました。日俳連組合員の男性175人、女性114人、性別不明28人の計317人から回収された集計(概略要旨)によりますと、「過去3年間に出演料未払いを経験した者」25%、「最近6ヶ月以上出演料支払いが遅れた経験」33%、「あらゆる出演作品について再利用料を求めたい者」92%という結果でした。切実な現実に直面している俳優の実態を知るにつけ、日俳連の果たす役割の重大性が感じられ、上記の世話人の中からは次代の日俳連理事会、常務会を担う人材が輩出されてきます。
文化庁・二次利用協議会への意見陳述
日俳連が芸団協の協力を得て、1992(平成4)年11月時点で、100人の俳優から回収したアンケートで、次のような結果が出ました。
出演時には簡単な口約束で書面契約は交わさない。 65%
映像作品の二次利用についての取り決めは交わさない。 79%
劇場映画でも二次利用に関しては報酬を支払うべきと考える。 83%
テレビ映画は放送用の作品だから、再放送料を支払うべきである。 83%
このことは、まさに俳優側から見た現行著作権法の矛盾点を如実に表しています。
そこで、日俳連と芸団協は1993(平成5)年4月16日に文部省(現・文部科学省)内で開かれた文化庁主宰の「映画の二次的利用に関する調査・研究協議会」(92年5月発足)に小泉博・芸団協専務理事(日俳連常務理事)、江見俊太郎・芸団協常任理事(日俳連常務理事)、棚野正士・芸団協事務局長を送り、アンケート結果を基にした意見を陳述しました。
その要旨を列挙すると
- (現行著作権法によって)隣接権制度上の実演家の権利は、放送事業者との関係では認められたが、映画の権利については無きに等しい。これは出演時の契約に全てを委ねるアメリカ的契約社会の方法に従っているためで、日本の実情を無視している。アンケート結果がそれを裏書きしているわけで、是非とも、現状の改善に効果ある法改正を検討してほしい。
- 現行著作権法では、映画に出演したときは、その映画における実演家の録音・録画権や放送有線送信権は働かないと定められている。この扱いは、実演家等保護条約(ローマ条約)第19条に準じたものだが、この条項に関して、1978(昭和53)年のWIPO(世界知的所有権機関)の条約解説書の中に「19条の厳密な適用が条約の精神に合致するかどうかは疑わしい。国内法がこの点に関して条約以上の保護をとくに実演家に与えるべきであると権威ある国際機関が勧告している」と述べられている。わが国の風土、慣習、力のバランス等を考慮すれば、実態に則した国内法を定めるのが当然と言えよう。
- 製作者に権利を集中させた現行法の立法趣旨は、多くの権利者の権利を束ねて(作品の)流通を円滑にするとともに、製作者がまとめて受け取った使用料を創造に参加した者たちに適正に分配することを期待したものと解される。しかし、実態は円滑すぎる流通や利用がある一方で実演家への配分は全く考慮されていない。しかも、放送番組であるはずのテレビ映画にまでそれが及び、さらにデジタル化により利用方法も多様化、複雑化するとなると、最早座視できない状況である。
- 実演家の権利処理は複雑で困難に見えるが、芸団協は加盟団体59団体(当時、現在は61団体)の協力の下に、レコードの二次使用料や貸しレコードの権利をはじめ、放送番組の隣接権処理の実績を長年にわたって積んでおり、放送事業者や外国の団体との間で80におよぶ協定や覚書を交わしている。映画関連でも声優やカラオケビデオの報酬の処理が日俳連できちんと行われている。
ということになります。言うべきことを、然るべき場所で明確に発言する。その実績はこのようにきちんと行われているのでした。
芸団協・実演家著作隣接権センターの設立
文化庁の「映画の二次利用協議会」で実演家側が発言したように、芸団協、日俳連は協力して映像作品の権利処理を行ってきました。しかし、現実問題としてまだまだ弱い実演家の権利を拡大し、擁護し、権利行使を集中して実行するためにはより強力な組織が必要になります。芸団協では、1993(平成5)年6月の総会で、この構想を会員団体に諮り、隣接権センター(略称CPRA=Center for Performers’Rights Administration)の設立に踏み切りました。主たる業務は「実演家の著作隣接権の処理に関する業務」「実演家の商業用レコード二次使用料に関する業務」「商業用レコードの貸与に関する業務」「私的録音録画補償金に関する業務」と位置づけられました。
映画対策協議会の結成
芸団協に関わる動きの中で、もう一つ、注目しておかねばならないのが「映画対策協議会」(映対協)の結成です。これまで繰り返し述べてきたように、劇場用映画がテレビ放送、ビデオなど多方面に利用されるようになり、便利さが追求される一方で、製作に関与してきた監督、メインスタッフ(撮影、照明、録音、スクリプターなど)、出演者の保護がなおざりにされている実情を是正するためにはどうしたらいいか。それを広い視野から検討し、各方面に働きかけていくための検討機関として設置したものでした。1993年7月30日に結成の会合を開き、会の代表には、日本映画監督協会の理事長、大島渚氏を選出。協議会は日本映画監督協会、日本メインスタッフ連絡会、芸団協の3者の代表者で構成するものとしました。俳優を代表する立場からは二谷英明氏、江見俊太郎氏、小笠原弘氏、小泉博氏、高城淳一氏が参画、協議会は毎月1度の会合を持ち、時宜に応じた問題への対処を続けました。
その後、2001(平成13)年からは、俳優の代表を日俳連常務の内田勝正氏、大林丈史氏、浜田晃氏に代わっています。
アテレコ振興作戦
外国映画の吹き替えやアニメーションへの声の吹き込みは俳優にとっての大きな仕事ですが、製作会社側にとってはコストのかかる問題です。「字幕スーパーで処理すれば、吹き替えの3分の1のコストで賄える」とプロデューサーは言います。では、映画の観客やテレビの視聴者にとってはどちらがいいのでしょうか。
「字幕をわざわざ読むのは煩わしい」
「字幕では字数に制限があり、台詞のニュアンスが表現できない」
との吹き替え派の意見がある一方で、字幕派からは
「出てくる俳優の元の声を聞くのが、ファンとしての楽しみ」
「完全に聞き取れなくても、しゃべり方を見ることでニュアンスが感じ取れる」
の意見が出されます。
他方、ヨーロッパではフランスやイタリアのように自国の国内法で「外国映画はすべて吹き替えにしなくてはならない」との定めを設けているところもあります。
日俳連に所属する声優の立場で、自らの職場を守るためにも、吹き替えの普及をより強く振興しようではないか、との気運が高まってきたのはこうした議論を踏まえてのことでした。アテレコ振興作戦と名を付け、日俳連外画動画部会の一大運動として展開しようとしたのも、こうした議論を裏付けにより有効な方法を見出そうと考えたからにほかなりません。
アテレコ振興作戦は、「調査」と「行動」の両面作戦で展開されました。
調査1では
外画動画部会内の調査部によって、テレビ創世期に果たした外国映画の役割とその後の状況の変化の把握
調査2では
専門家を擁する研究機関に委託して「字幕で表現できる情報量」「ブラウン管のサイズによる文字量の変化」「字幕を読む際の視聴者の目の動きとそれに伴う疲労度」「字幕が好まれる作品、嫌われる作品」を明確にする。
調査3では
やはり専門家による調査で「アテレコで表現できる情報量」「アテレコの長所と短所」「アテレコ向きの作品、不向きな作品」を明確にする。
そして、このための外画動画部会の行動として
行動1では
アンケートの設問製作、アンケート対象の確定、集計を。
行動2では
一般マスコミを利用した視聴者へのアピール。
行動3では
外国製作会社、外国映画配給会社への働きかけ。
をそれぞれ担当することにしました。
未払い出演料対策会議スタート
1993(平成5)年11月1日、日俳連と日本音楽家ユニオンが協力して問題解決に当たる新しい組織「未払い出演料対策会議」が発足しました。出演したのに出演料を払ってもらえない。といって製作会社に強気で要求することも出来ない、といった悩みを抱える人に親身になって相談に乗ろうという組織です。問題解決のためには弁護士に相談するケースもあるでしょう。その場合には相談料のサービスも致しましょう、という趣旨でスタートしたのです。
日俳連は言わずと知れた俳優による協同組合、日本音楽家ユニオンはオーケストラなどで活躍する演奏家の労働組合です。双方とも実演家の権利を擁護、拡大し、生活の安定に向けて活動を展開するという意味では同じ目的を持った組織ですが、別々のジャンルで働く実演家が同じ目的で二人三脚を組むのは珍しいことでもあります。また、この新しい対策会議には、東京法律事務所、旬報法律事務所から働く者の権利を守る立場で活躍するベテランの弁護士が4人も参画してくださいました。
スタート時点の役員は日俳連側が池水通洋氏、小笠原弘氏、江見俊太郎氏、高城淳一氏、玉川伊佐男氏の各常務理事、音楽家ユニオン側は松本伸二・代表運営委員をはじめ佐藤一晴氏、日下文夫氏、安並克磨氏ら各運営委員の方々。また、弁護団は東京法律事務所から永盛敦郎氏と水口洋介氏、旬報法律事務所から清水恵一郎氏、中野麻美氏で構成。事務局は日俳連の十嶋赫子氏と音楽家ユニオンの鈴木稀王氏が当たることになりました。
この対策会議の発足を「日俳連ニュース」で伝えると、早速3ヶ月の間に3件もの相談が持ち込まれました。ナレーションに出演したのに払ってもらえないフリー俳優のケース、Vシネマに出演しながら1年間も未払いで放置された俳優4人のケース、それに劇場映画出演後、未払いで放置されたケースです。日俳連組合員の素早い反応に喜ぶ反面、深刻になっている未払い問題に直面して、改めて驚かされた対策会議のスタートでした。
私的録音補償金制度の発足
「私的録音補償金制度」とは、家庭や同好の士のグループがラジオ、テレビ、CDなどから自分たちが楽しむ目的で録音をするために機器を購入する場合、機器の売値に一定の比率の上乗せをして、その上乗せ分を演奏したり、歌ったりしている実演家に補償金として分配しようという制度です。ただし、価格上乗せがあるのはデジタル録音機器の場合だけ。具体的にはDAT、DCC、MDの3種類(98年11月からこれにオーディオ用CD-RとCD-RWが加えられ5種類となりました)です。そして一定の上乗せ比率は、録音機器が2%、記録媒体が3%となっています。
著作権法では、原則として市販のCD、テープ、ラジオ、テレビから無断で録音することを禁じています。しかし、滅多に聴けない名演奏や沢山の曲が録音されたCDからお気に入りの名曲だけを別に録音して楽しみたい、という気持ちは誰にでも働きます。そこで、商売に使ったりするのでなく、家族や仲間内で楽しむ分には対価を支払わなくても録音して利用してもよい(著作権法第30条)の規定を設けているのです。
ところが、録音機器の技術が改良され、新たな機器が開発されて、デジタル機器の時代に入ってくると、アナログ時代と違って記録媒体に録音した音質が何時までも劣化しないようになってきました。そうなると、最初に録音物に固定化する際に演奏した実演家は、一回の演奏の成果をほぼ永久に楽しまれてしまいます。これではいかにも実演家側に不利だというわけで、1992(平成4)年12月、著作権法の一部が改正され、上記のような機器の売値に一定比率を上乗せして消費者に、実演家への補償分を負担して貰う制度を作り出したのです。この「私的録音補償金制度」は、93年6月から実施され、さらに6年遅れて99年7月から「私的録画補償金制度」がスタートすることになります。