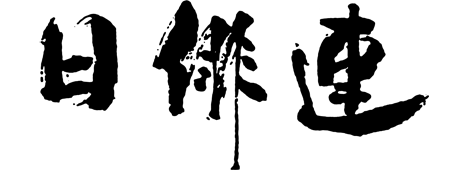-1995年- がんばろう!!神戸
1995(平成7)年1月17日早朝、神戸から淡路島にかけての広い範囲でマグニチュード7.8という極めて大規模な地震が発生しました。歴史に残る「阪神大震災」です。神戸市で起きた火災の被害も含めて、死者は6000人にも達するという歴史上の大惨事となりました。幸いにして日俳連組合員の中には死傷に至る犠牲者は出ませんでしたが、住居を破壊されるなどの被害を受けた人は10数人にのぼりました。
その当時の様子を、神戸在住の組合員、堀内正美氏は「日俳連ニュース」62号(95年3月1日付け)で、次のように記しています。
私は、昨年(94年)4月から出演している生ワイド「おはようラジオ朝一番」のオンエアー局、AM KOBE 558(ラジオ関西)に駆け付けた。大震災の起きたその朝も当然スタジオ入りしなければならなかった。神戸市須磨区の海岸沿いに位置するその局は、震源に最も近いラジオ局であり、崩壊の危機にさらされている。現に建物の中に足を踏み入れてみると、最近どこかのテレビ局で見たロシアに攻撃されるチェチェン共和国の自由放送局のような様相を呈している。4つあるスタジオもすでに3つまでは使 不能な状態になっていた。
いまにも崩れ落ちんばかりのスタジオの中からスタッフが伝えようとしたのは安否情報とライフラインにかかる情報であった。スタッフの大半が被害者であり、パーソナリティーも少なからず被害を受けている異常状態の中では情報の伝達は自分自身の生命の維持装置でもある。078(733)0123は被災地の市民と非被災地の市民を結ぶホットラインである。6代の電話機は絶えることなく鳴り続いた。そして、その1台の受話器を取った時であった。聞こえてくる声は自分の息子を捜す被災した母親の声であった。恐怖と不安で引きつったような泣き声は悲痛な叫びでもある。「いいよ、いいよ。落ち着くまで泣いていいよ」「がんばろう、がんばろうね」応対しながら私の口から出る言葉はこれしかなかった。そして、母親からのメッセージの代わりに「〇〇君、元気だったらここへ連絡してください。お母さんが捜していますよ」とマイクに向かって叫んだのだった。
堀内氏は、この経験を基に、ボランティア活動に専念しようとします。とく被災者の心を癒すボランティアを重視し、「がんばろう!!神戸」を組織し、日俳連組合員はもとより広く全国から物心両面の寄付を求めるのでした。
ところが、そうする堀内氏に地元の人々からは異論が出されたのでした。堀内氏は「日俳連ニュース」の中で、さらに続けます。
この声によって、私は名古屋への出発を決意した。そしてその舞台からのメッセージは、奇しくも現代人が忘れかけている「人間の優しさ、強さ、思いやりを訴える芝居」である。
役者としての使命を、被災者が教えてくれるという感動的な話と言えましょう。
日俳連では、全国の組合員に呼びかけて被災組合員への義捐カンパを募りました。その結果は約800人から650万円を超える義捐金が集まり、被災の程度に応じて分配しました。一方、外画動画部会では一般被災者に向けてのスタジオ・カンパが実施され1月25日から2月5日までの間に50万円が集まりましたので、これを田原アルノ委員長と野沢雅子さんが代表となって、東京・築地の朝日新聞社に届けました。
方言シンポジウムの開始
1995(平成7)年5月6日、東京・渋谷区富ヶ谷の青年座で第1回方言シンポジウム「ドラマの中の方言を考える」が開催されました。長年にわたって交渉した結果、前年4月にやっと出来上がったNHKとの方言指導料の支払いに関する制度を一つのきっかけとして、日俳連内部にも、また一般の方々にも「方言指導の重要性」を知って貰おうと企画したものでした。折良く芸団協からイベント開催の助成金が戴けたのも、開催の大きな原動力になりました。
心配された参加者の数は、当日になって完全に解消されました。青年座劇場の250席は埋め尽くされ、立ち見さえ出る盛況となったのです。森繁理事長自らの出演で会津弁の朗読があるとか、永六輔さんの講演があるとかも参加者にとっては大きな魅力だったに違いありません。しかし、それ以上に「方言」そのものに深い関心があり、どこにどんな言葉があって、どう使われているのか、を知ろうとする参加者の意欲が感じられたものでした。
このシンポジウムでは、先ず、森繁理事長が福島県出身の医師、見川鯛山氏の作による「婆っぱ」の朗読をして始まりました。「婆っぱ」とは、93歳になるオ辰婆さんが医者に「あと2、3日の命」と引導を渡されてから2週間も生き続け、最後には大飯を食らって死んでしまうというユーモラスな物語です。いわゆる会津弁で書かれているために、方言のイントネーションを駆使して朗読してこそ面白味が出るというものです。訛りを加えたうえ、森繁調といわれる独特の調子での朗読には、場内が、しーんと静まりかえったものでした。
方言の実演では、車寅次郎で有名な映画「男はつらいよ」シリーズから、特徴ある一場面を取り出し、寅さんと家族のやり取りを青年座の俳優たちが大阪弁、山形弁、熊本弁、名古屋弁で実演して見せました。風来の旅から帰ってきた寅さんと団子屋の家族が夏の夜に西瓜の分け前を巡って喧嘩するシーンも原作である江戸弁とその他の地方の言葉では、雰囲気が大きく違ってくる様子と、いくらプロの俳優が演じても方言指導者から見ると不満の残る辺りを、参加者である観客には心ゆくまで堪能していただきました。
そして、最後は永六輔さんの講演で「方言の役割」。戦時中の沖縄では、土地の人同士が沖縄言葉で話し合っているのを見た旧日本軍の兵士が、内容が分からないところから、スパイの嫌疑をかけ、殺してしまったという悲劇さえあったといいます。そんなエピソードを交えながらの講演は、時に聴衆に感動を与え、時には爆笑の渦となって大変な好評でした。こうして成功した方言シンポジウムは、以後毎年1回テーマを変えて、必ず開かれることになります。とくに、1997(平成9)年からは、津野哲郎理事の紹介で協力を仰ぐことになった京浜東北線・大森駅前の大森・東急インから会場の提供をいただき、毎年同じ会場での定期開催になっていきます。
俳優による「チャリティ美術展」の開催
阪神大震災の復興と義捐に向けたチャリティ活動をしたいという気運は、この年の春になっても続き、常務会、理事会でも考えた末、美術展を開催しようということになりました。それに、若者世代に高まっているアニメーションの人気に応えるイベントの展開も必要だろうということから、この二つを合わせて進める企画が進められました。名付けて「芸能人・文化人によるチャリティ美術展」。開催に当たっては理事であった白石奈緒美氏とそのご主人である中島力氏(704プロジェクト代表取締役)が尽力してくださり、東京・銀座の日動画廊、テレビ朝日の事業部が後援をしてくれました。
もちろん、この美術展は阪神大震災だけにとらわれて企画されたものではありません。元を質せば、日俳連の存在感を世間に知らしめるため、組合員の参加意識を高めるため、世の中に直接役立つ事業を展開するため、と多方面から問題を考える中で生まれてきた構想だったのです。話が具体化し始めたのは94年の秋頃からでした。
「俳優の中には多才な人が沢山いる。とくに美術に関心を持っている人は多い。絵画や彫刻を集めて展覧会でも開こうではないか。もし、買い手が付いて売り上げが上がったら、近づく高齢化社会に役立つ寄付にしてもいいではないか」
こんな議論から、白石理事が「銀座の日動画廊に協力を依頼してみよう」と動き出してくれたのでした。また、白石氏のご主人、中島氏は元テレビ朝日のディレクターでしたが、顔の広い方で、テレビ朝日社内はいうまでもなく、厚生省(現・厚生労働省)の外郭団体である全国社会福祉協議会にもコネクションを持っていて、チャリティのあり方についても適切なアドバイスを下さいました。そこで「それでは、いよいよ展覧会に向けて動き出そうか」との意見が理事会内でも集約された矢先、阪神大震災が発生したというわけだったのです。
大震災の発生で、チャリティの目標は明確になりましたが、今度は事を急がねばならないというジレンマに取り付かれることになりました。先ず第一は、俳優で絵画、彫刻を得意とする人は誰なのか、どの程度の腕前なのか、果たして快く出品に応じてくれるだろうか、の問題です。それに作品の大きさが分かりませんから、第二には作品の運搬作業をどうするのか、さらに第三には、買い手が付いた場合の売上高を全額寄付に回してよいのか、一部は作者に還元すべきなのか、場所を提供してくれた日動画廊にはどう対処すべきか、との問題も出てきました。そして、心配はその通りになりました。日俳連の組合員だけでは作品の数が十分ではなかったのです。結局は弁護士や浪曲師、シャンソン歌手、映画美術監督、詩人という方々にも、あらゆるコネクションを活かして出品を依頼することになったのでした。
実行委員会はチーフを高城淳一常務理事とし、それに大林丈史氏、福山象三氏、白石奈緒美氏の三理事、さらには粟津號氏、坂俊一氏、島田敏氏、竹村拓氏、田村円氏、金野恵子氏、一城みゆ希氏らが委員として参画しました。
そして集まった作品は絵画、書道の部門で78人、175点、色紙の部門で76人、275点にも達しました。彫刻や焼き物を出品したいとの希望もありましたが、作品の取り扱いになれていないため運搬中に壊したりしたら大変と、ご遠慮申し上げました。
この美術展で大きな特徴をなしたのは、何と言っても、若いアニメファンを対象に独自のイベント会場を併設したことです。日動画廊にはメインの展示場の裏にアネックス日動画廊と名付けられた20畳ほどの小さな展示室がありました。日俳連では、そこを「第2会場」に当て、アニメファン対象のサイン色紙とセル画の即売を実施したのです。セル画とは透明のセル(透明のフィルム)に何枚も何枚もの絵を描き、その絵によって人物や動物の動きが表せるようになっている原画のことです。言ってみれば、人間が一枚一枚書き上げたフィルムのようなもので、ファンにしてみれば、是非とも入手したい、またそれに声を入れている声優の色紙によるサインを合わせて入手できれば最高、という代物でした。
この企画をこなすに当たって、連日徹夜の準備をしたのが島田敏氏をキャップにチームを組んだ外画動画部会の仲間たちでした。ハイティーンを中心としたアニメファンに、どうやってこのイベントをPRするのか。色紙やセル画は何枚用意すればよいのか。値段はいくらに設定すべきなのか。チームは何度も何度も会合を繰り返し、アニメ雑誌への投稿原稿の執筆や深夜のラジオ番組に出演している仲間に番組の中でしゃべって貰う依頼などを繰り返したのです。会場の銀座に近いということで東京・晴海の公団団地に出向いてビラ配りもしました。
1995(平成7)年7月28日午前9時、日俳連初体験のチャリティ美術展は3日間の日程で開幕しました。そして驚くべき事態に直面したのです。熱狂的なアニメファンは前日の深夜から画廊の前に行列を作ろうとしたからでした。雑誌やラジオで美術展の予告PRを始めてから、事務局では問い合わせに備えて特設電話を設置し、1日中鳴り続ける電話に驚いていたのですが、開幕前日に行列が出来るとは予想の範囲を超えていました。夏の最中で、病気を心配する必要はないものの放置しておくわけにはいきません。そこで、その夜はお引き取り願い、翌朝早朝の受付を約束したのですが…。
翌朝、7時にはもう50人ほどの列が出来てしまいました。少しでもいいセル画を手に入れよう。目指す声優のサイン色紙を確保しよう、との狙いなのでしょう。若い彼ら、彼女らのエネルギーにはほとほと押される思いだったのです。このエネルギーは日中になるとさらに高まりました。今度は、長く延びる行列の中から日射病や熱射病が起きる心配が出てきます。整理に当たっていた外画動画部会の委員は、行列をつくる若者に「整理券」を渡し、決められた時間に出直すよう促して混乱を回避しましたが、この整理券を配り、説明する部会の委員の方が熱射病にやられないかと心配するほどの騒ぎになってしまいました。
大きなイベントをやると、全く予想もしない事態が生じるものです。売れた人気声優のサイン色紙が1時間後には、銀座の歩行者天国で商品として出回っていたのです。色紙は子ども相手に売るのだから、会場で直接書いてもらったものでも1枚2000円を限度、と考え、検討して値付けしたのに、歩行者天国に出回ったときにはもう5000円の値が付いていたのでした。
諸々の心配や小さなトラブルは起こしながらも、美術展は3日開催され、ともかく100万円の純益をあげることが出来ました。このお金は高城常務の手によって全国社会福祉協議会に届けられました。
吹き替え40周年大懇親会
日本で本格的にテレビ放送が始まったのが1953(昭和28)年。やがて50年代後半になりますと、昔懐かしい「アイ・ラブ・ルーシー」「名犬ラッシー」「ハイウェイ・パトロール」など外国映画の日本語版が盛んに放送されるようになります。1960年には、その主題歌が大ヒットした「ローハイド」や「ララミー牧場」が24.2%、31.5%もの視聴率をあげた記録もあります。アテレコをする俳優は超多忙となり、女房、子どもの顔を見るより仲間と顔を合わせている時間の方が長いといわれた時代が来たのでした。こんな時代を体験した人が集まって1994(平成6)年11月27日には東京・渋谷の支部や勤労福祉会館で昔を懐かしむ「名声会」なる親睦会が旗揚げしました。
ところが、これだけでは満足しきれないとの声が出始め、バブル崩壊の不景気を吹っ飛ばすためにももっと大規模に盛り上げる会をということで、1995(平成7)年10月9日、今度は東京・九段下のホテル・グランドパレスに俳優、マネージャーを集めた大パーティーを催すことになったのです。272人も集まった参加者は意気軒昂。アテレコの発展を誓い合って喉を潤したのでした。