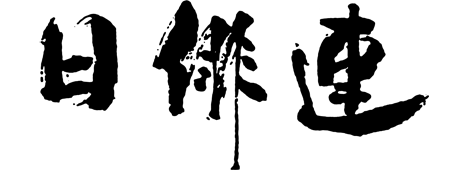チャリティ事業の数々
俳優団体連絡会 殿
「朝日・明るい社会賞」は、世の中を明るく、楽しく、住み良くするため、すぐれた善行をを行った人または団体に、朝日新聞社がお贈りする表彰です。朝日新聞の昭 和40年2月18日付け紙上に報道されたとおり、あなたがたは、暴力団の関係する興行を公共施設から締め出して資金源を断ち切ろうとする動きに呼応し、「芸能人自身 も暴力団から完全に絶縁しよう」という日本映画俳優協会の呼びかけにこたえて、勇気にみちて約束しました。この動きは、連絡会所属の六団体ばかりか、芸能界の各分野にわたって幅広くひろがろうとしています。
この業績は、「朝日・明るい社会賞」の趣旨に該当するものと認め、ここにこれをたたえ、規定によって本賞を贈ります。
昭和40年3月
朝日新聞社
この賞状は、1965(昭和40)年3月11日、東京・麻布の麻布国際文化会館ロビーにおいて、朝日新聞社企画部から俳団連に贈られたものです。
これより先、俳優、とくに映画俳優は暴力問題であらぬ誤解を受け、トラブルの渦中に置かれていました。例えば、京都新聞(1965年2月23日付け夕刊)は、3人の大学教授と同新聞社の編集参与で「いいたい放談」なる座談会を企画し、
A どうも芸能に暴力は断ち切れないんだな。日本人はつまらない芸能人にでも無我夢中になる。へんな歌うたいがくると、ミーハー族は気違いみたいに押し掛けて大変な騒ぎだ。ああいう芸能ファンが暴力団の予備軍になるんだ。
B あんなに芸能に大衆動員できるのは、日本だけだろう。楽しみが少ないからね。
C だいたい日本の演劇は、各地の小屋まで全部いわゆる顔役が経営していた。だから、暴力団と興行とは結びつきがある。芸能人もそういう陣営に属する人間だから、顔役に頼らないと成り立たない。
D 芸人も暴力団も似たようなものだ。芸がなければ暴力団になるか、暴力団の中で芸の上手なものが芸人になるかどっちかだ。
などというデタラメな記事を掲載しました。俳優が怒るのは当然です。映俳協、俳団連では早速「俳優全般にとって職域的、社会的名誉の侵害だ」として善処方を求めました。
一方、俳優個人でもトラブルに巻き込まれるケースが出ました。当時、若手を代表するスター俳優だった石原裕次郎氏が銃砲刀剣等不法所持の疑いで自宅、石原事務所等を家宅捜索されたのです。石原氏の釈明によりますと、実はピストルの密輸に関わって逮捕された暴力団員Mが「自分は石原裕次郎の用心棒である」などと世間に吹聴していたことから、火の粉が飛んで「関係者」にさせられてしまったのでした。石原氏は釈明をするとともに、声明書を出して、事実無根の誣告を受けた不名誉と基本的人権擁護のために、断固、闘う旨を表明しました。
朝日新聞社からの賞状は、こうした俳優たちの行動に対してなされたものです。当時の朝日新聞は、新聞の第1面「天声人語」欄でも「立ち上がった芸能人の勇気と決断」として礼賛しています。
クイズ番組への大挙出演
1965年当時、フジテレビの人気番組の一つに「地上最大のクイズ」というのがありました。スタジオの中に100組200人もの回答者がひしめき、クイズに次々と答えては勝ち抜き合戦を演じるという番組でした。この番組に大量の俳優を送り込めば、番組は華やかになります。また、放芸協とすれば、この番組に大勢の出演者を出すことによってフジテレビから助成金を受けられるというメリットがありました。
放芸協では、この番組に100人の出演者を送り込むべく、実行委員会を結成しての対処となりました。理事会による選出で選ばれたのは
実行委員 水の江滝子
大平透
江見俊太郎
村瀬正彦
の5人。綿密な協議のうえ、結果は200人を超える出演者に依頼して、クイズは放芸協大会として収録は無事終了。約100万円の助成によって財政不安も一段落という事態になりました。
ただ、これには一つのエピソードがあります。
クイズに出場した中には後に日俳連の理事長に就任する佐々木孝丸氏も含まれていました。佐々木氏といえば、俳優仲間では、切っての物知りであり、インテリでした。戦後、労働運動の盛んな頃には、どこの労組でも歌った労働歌「立て!飢えたるものよ」の日本語作詞者であり、ドイツ語にも堪能でドイツ戯曲の翻訳や演出も手掛けた人でした。
「クイズでは、佐々木さんの優勝だよ」と誰もが噂をしていました。
なのに、佐々木氏は2、3問答えたところで失格してしまったのです。
設問は「かもねぎ」というのは、鳥の鴨が葱(ねぎ)を主食としていること、合ってるか、間違ってるか、でした。それを事もあろうに「合っている」と答えてしまったのです。「猿も木から落ちる」を地で行く失敗でした。
正解は、誰でも分かっていますよね。鴨南蛮そばにはネギの薬味が合うという意味から、「鴨がネギを背負ってくる」つまり「お誂え向き」となるわけです。
その他、チャリティ関連では1964年6月に発生した新潟地震の被災者救援を目的に行った東京タワーでのチャリティ・サイン会、1965年8月に行った「全国重症心身障害児(者)のための愛のバザー」も記憶に止めておきたいイベントでした。
関西との連携
東京を中心に、放送に関係する芸能実演家を結集して出来上がった放芸協は、結成ほぼ2年間で、会員約700名を数えるほどになりました。満足な発展とはいえないまでも、まずまずの組織強化でした。そこで、次に問題になるのが東京以外の地で働く実演家をどう組織化していくかです。
1965(昭和40)年4月、当時常務理事であった江見俊太郎氏は、仕事の関係で関西に出向いたのを機に、関西在住ながら早くも放芸協に入会していた毛利菊枝氏をはじめとして、道井恵美子氏、夏目俊二氏(ともに関西芸術座)、梶川武利氏(ぐるーぷ・やまなみ)らとの懇談の場を設けました。東京の実情を伝えると同時に、関西での関心の度合いを知るのが目的でした。
放送の芸能部門で働く人数は少なくとも、自主的な組織を持ちたいとの気持ちは、関西に住んでいても同じです。また、放芸協としては総会で関西支部を設置するという基本方針は決まっていました。というわけで、関西では早急に支部結成に向けての具体的な話し合いを開始すること、同年6月11日に予定されている大阪での著作権制度審議会の説明会に俳優ができるだけ沢山参加すること、などを申し合わせたのでした。
動きは、予想以上に、早く進みました。同年7月22日、大阪にある松竹芸能の会議室に東京から出張した常務理事の大平透氏、事務局長の村瀬正彦氏を囲んで関西の演劇グループの代表10数人が意見交換を行いました。さらに、同年8月9日には、東京に出張してきていた名古屋放送芸能人懇話会の谷口徹次氏、柾木卓氏が、放芸協の事務局で常務理事の久松保夫氏と懇談。当面する著作権問題を中心に俳優の抱える課題の整理を行いました。
「俳優の著作権」俳団連の記者会見
俳優の権利を守るための史実として是非とも記録に残しておきたいことが二つあります。一つは文部大臣の諮問機関である著作権制度審議会の審議経過について俳優の立場での見解を示した1965(昭和40)年5月22日の文部省記者クラブでの記者会見。そして、もう一つは俳優の立場の見解を論文にして書き残した「忘れられていた著作権」なる著書の発刊です。
1962(昭和37)年に設置された著作権制度審議会は、第4小委員会で映画問題を、第5小委員会で隣接権問題を審議するという分離形式をとってきました。その結果、出た結論は…。
一方では「俳優の創作行為は隣接権の問題として検討されるのが適当であり、映画的著作物の共同著作者の中から除外して論を進めること」とし、他方では「映画的著作物に出演した実演家には隣接権制度上の保護の規定は適用されない」であったのです。要するに、二つの小委員会とも、映画についての俳優の保護は何一つ考慮しようとはせずに、全てを製作者と出演者の「契約」に委ねようとしたのです。当時、大資本の一角と言っても過言ではなかった映画会社に一俳優が契約で権利の確保を認めてもらおうとしても、所詮、無理な算段。俳優が下手に要求を突きつけたりすれば、会社から「出演したくなければしなくて結構」と言われるのが落ちでした。しかも、二つの小委員会の解釈では「映画的著作物および映画に類似する方法で得た著作物」と一束ひとからげに映像作品を括り、劇場映画もテレビ映画も、さらにはビデオテープにも俳優の権利が及ばないように結論づけていたのです。俳優側に一切の権利を認めないのは如何なる理由によるものなのか。この立場で、俳団連は記者会見に臨んだのです。
会見で俳団連が表明した見解は次の7項目に集約されました。
- 演技は、演技者の無体財産であり、他人の侵害から守られなければならない。従って実演家には許諾権、禁止権が与えられるべきである。
- 演技を固定したものの二次的利用は、如何なる場合も、実演家に許諾・禁止権、報酬請求権、人格権の保護が補償されるべきである。
- バラエティ・アーティストを保護の対象からはずしてはならない。
- 映画著作物は、映画の制作に創作的に直接関与したものの共同著作物である。演技者は、その演技創作をもって、映画の制作には欠くことの出来ない創作的関与をしているのだから、共同著作者の一人である。
- テレビ映画は、一般に劇場用映画の10分の1程度の制作費で作られる。これを再利用や劇場用への転用の際も、実演家の手の届かぬところで行うのは不当である。
- ビデオテープは映画的著作物ではなく、放送用の固定物として考えるべきである。
- 外国映画日本語版の録音テープは、あくまでも放送用の音的固定物として、原画は別個の扱いをすべきものである。
名著『忘れている著作権』
タクシーの運転手さんがいいました。
「旦那、毎日みてますよテレビ。……あゝ毎日じゃァ蔵が建っちゃいますよね」
「あれは君、昔のものを断りもなしに、またやってんだよ」
「でも、頂くものだけはガッポリ頂いてんでしょ。ならいいじゃない」
「冗談じゃない。一銭も払ってくれやしませんよ。放送会社は…」
「だって、スポンサーついてましたよ、新しいのが。……だったら、おかしいじゃない」
「おかしいさ。だけど、くれないんだな」
「そんな馬鹿な。旦那、それで黙ってんの?」
「ウン、まぁね」
「へッ、そんなもんかねえ」
「あゝ、そんなもんだよ」
税務署の人がいいました。
「昨年はだいぶお忙しかったようで…」
「いえ、まるで暇でした。リピート放送ばかり増えたもんですから」
「は?」
「あれみんな、無断・無報酬の2度、3度のおつとめなんです」
「それ、本当ですか?」
「ウソだと思ったら、調べてごらんなさいよ」
「……はァ」
これは、1965年6月、日本放送芸能家協会・著作権委員会編、放芸協発行で発刊された非売品の著書。その「まえがき」の冒頭に記されているエピソードです。まったく現在でも通用するこのエピソードで書き出された著書は、その副題にあるように「芸能人は法律でどのように護られているか」を論じた名著です。委員会編とし、筆者個人の名前が明確にはなっていませんが、著者は久松保夫氏だったのです。
20世紀の初頭、日本では明治の末期といった方が分かりやすいでしょうか。浪曲師で桃中軒雲右衛門という人がいました。本名・岡本峰吉。長髪をたなびかせ、入道と呼ばれる浪曲師でした。その雲右衛門が34歳だった1906(明治39)年のこと。東京本郷座で演じた「赤垣源蔵徳利の別れ」「南部坂雪の別れ」が爆発的な人気を博し、定価1円也のレコードとなって発売されたのでした。
ところが、その五年後、同じレコードが25銭也の超廉価で巷にあふれ出るようになりました。悪徳商人による海賊版の発売でした。怒ったもとのレコード会社(横浜のドイツ国臣民・リチャード・ワダマン)は、訴え出て裁判になりました。これが、日本の著作権史上つとに有名な「雲右衛門の浪花節レコード不法複写に関する係争事件」でした。
裁判の結果は、1912(大正元)年11月11日、東京地裁で出され、雲右衛門は勝訴しました。「浪曲の口演はそのままで著作物であり、被告は1000円の損害賠償を支払わねばならない」の判決でした。しかし、被告側は抵抗して上告までしたため、大審院第3刑事部は1914(大正3)年7月4日、逆に訴え出たレコード会社に敗訴の判決を下したのです。
これが判決理由でした。
しかし、この大審院判例には当時の学者の間にも批判がありました。また、敗訴では収まらないレコード会社も当時の衆議院議員で、第二次大戦後には総理大臣になる鳩山一郎氏を動かしたりして、1920(大正)年に議員提出法案を作り「レコードにも著作権がある」との法改正を実現したのです。こうなると、レコードの中身である演技者も保護しなくてはならないとの議論に発展します。その結果、著作権法第1条には「文書」「演述」「図画」「建築「彫刻」「模型」「写真」「美術」と並んで「演奏歌唱」が著作物に加えられ、「著作物の著作者はその著作物を複製するの権利を専有す」と定められたのでした。これで、浪曲師は著作者になりました。
しかし、そうなると落語、舞踊、俳優の演技はどうなるのだとの疑問が、当然、出てきます。さて、ではどうなっているのか。「忘れられている著作権」は、実演家も「著作者」なのだと言うことを、当時の著作権法(旧著作権法)を解説しながら、明らかにしているのでした。まさに、実演家の権利に関して問題提起をした名著でした。「俳優にとっての旧約聖書」などと言われるのもこうした内容によるのでしょう。
名古屋放送芸能家協議会の発足
1965(昭和40)年12月、名古屋を中心とした周辺の東海地区に在住する放送、映画、舞台の俳優による組織が発足しました。「名古屋放送芸能家協議会(略称・名放芸協)」です。
この前年、東京ではオリンピック東京大会が開催され、これにタイミングを合わせて、東京~新大阪間には東海道新幹線が開業しました。首都・東京と商都・大阪を、それまでの東海道線超特急で8時間かかったものを、わずか3時間強で結んでしまうという交通革命が起きていました。「名古屋はもう必要のない都会になるのではないか」「東京と大阪への人口集中で名古屋は空洞化するのではないか」など、取り越し苦労な議論が巻き起こっていた頃でした。
「冗談ではない。東海地域は独自の文化をもつ大切な場所柄だ。俳優は結束して待遇改善に当たろう」というわけで、100人足らずとはいえ、十分な意気込みでスタートしたのです。理事長には舟木淳氏を選出し、結束と同時に芸団協に加盟しました。