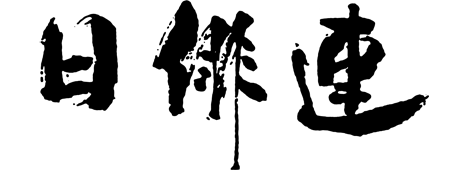-1983年-
アメリカ産エンターテインメントのシンボルともいうべき「ディズニーランド」が4月15日、千葉県浦安市で営業を開始しました。それは日本における消費生活の向上を象徴する現象でもありました。しかし、一方ではこの年に国債の発行残高が100兆円を突破するという経済危機の予兆も見えてきていました。
実用静止衛星の打ち上げ成功
1983(昭和58)年2月4日、日本では初の実用静止衛星が打ち上げられました。これによって、いよいよ日本でも、本格的な衛星通信の時代に入ることになったのです。ニューメディア時代の幕開けともいうべき快挙でした。通信衛星の打ち上げに続いて、翌1984年には実用放送衛星の打ち上げが予定されています。そして一つの衛星の寿命が尽きれば、また次の衛星打ち上げが予定されるというわけで、衛星放送は年を追って本格化していくものと期待されました。
衛星放送が本格化すれば、放送のチャンネル数が増える。そうなれば放送用ソフトが必要になり、ドラマの収録も増えるのではないか。そんな淡い期待が俳優の中にも生まれました。しかし、実態は、決してそんな甘いものではなかったのです。
芸能人懇親大パーティー
この年の5月27日午後6時、東京・永田町の赤坂プリンスホテル新館クリスタルパレス宴会場では、俳優、マネージャー、製作会社、その他芸能関係者1500人が参集しての大パーティーが開催されました。パーティーの名目はマネ協の創立10周年を記念するものでしたが、そこには単なる記念行事に止まらず、芸能人の気概を見せようとの意図も含まれていました。パーティーが開催される前の4月2日付け東京中日スポーツ新聞は「芸能界が空白の1日を作る」として大きな特集記事を載せています。
それによると、「空白の1日」とは俳優、マネージャー、製作関係者を一堂に集めることによってドラマの制作をストップさせてしまおうとの狙いを表現したものだ、というのです。では、何でそんなことを企画したのでしょうか。
1982年の中村プロや勝プロの倒産の例でも記したように、テレビ・ドラマを巡る情勢は厳しいものでした。視聴率競争の激化に伴って1部のタレントにばかり需要が片より、俳優全般の仕事が減ったところからマネージメント・プロダクションの中にも危急存亡という言葉が如実に当てはまる事態が生じていたのです。ドラマのキャスティングを取り巻く環境は荒れ放題となり、格安で出演依頼をしてくる放送局に対して苦情を突きつけていると、すぐに別のタレントに話を持っていかれてしまうような例が次々と出てきてしまっているのでした。
垣内健二理事長をはじめ千葉哲也事務局長、平田昆パーティー実行委員長らマネ協の幹部はこうした状況を憂い、「マネ協の団結力および意外的な力を天下に誇示すること」を目的としながら、芸能界に働く者の社会的地位向上の足がかりを作ろうとしたのです。当日は日俳連の理事長、佐々木孝丸氏と次期理事長として近く交替の内定している森繁久彌氏も参加し、お二人が壇上で堅く握手を交わすなど世間にもその存在を広く伝えました。
理事長の交代
話が後先になりましたが、佐々木理事長から森繁理事長へのバトンタッチは、1982(昭和57)年10月29日の第17期通常総代会の席で確認されたことでした。佐々木氏がすでに80歳を超える高齢に達しており、健康もすぐれないことから「是非とも森繁さんを後任に」と希望され、この総代会の時点では理事になっていなかった森繁氏は、先に久松保夫氏の死去によって欠員を生じていた理事の補欠として総代による推挙を受けていたのでした。森繁氏は、総代会後の理事会で早速理事長に選出されました。
映像対策委員会の発足
前年、仇役懇親会として産声をあげた有志の会は8ヶ月の期間を経てテレビ・ドラマに関わる諸問題を検討する「映像対策委員会」へと発展的に組織変えを行ったことは前述したとおりです。この時代、日本の俳優のうち78%の人々はテレビ・ドラマを主たる職場として活動しているといわれていました。ところが、民放で放送されているテレビ・ドラマは、その90%以上が放送局自身の手で制作されるものではなく、外部に下請け発注されて作られていいるのでした。それどころか、受注した製作会社はさらに孫請け会社に制作を任せるという事態も多々あったのです。発注が下請け、孫請けと進めば俳優の出演条件は悪くなり、ギャラも低額になる傾向があります。そのうえ具合が悪いのは、放送局以外の制作会社で制作されるドラマは「テレビ映画」と称され、映画であるから再放送されてもリピート料の支払いがなされることは、極く少数の例外を除いて、ありませんでした。
また、こんな実態もありました。1979年には41本放送されていた1時間物のテレビ映画が、1983年時点では18本にまで激減し、その分俳優の働く場が減少しているのでした。映像対策委員会は、こうした現状にどう対処していくべきかを検討する場として設定されたのです。「日俳連組合員の声優は、全員、外画動画部会に所属し、結束して事態の解決に向けて行動している。その結束の力で、過去には待遇改善も実現してきた。映像部門も同じように行動できないのか」――そんな気持ちも働いていたのでしょう。1983(昭和58)年12月9日には、芸団協会議室に15人の有志が集まって対策委の第1回常任委員会を開催しました。
もう一つ、と言うよりもこちらの方が重要だったのかもしれませんが、当時の映像対策として重視しなければならなかった問題はビデオ産業の急成長への対応でした。なにせ、1978(昭和53)年から1982(昭和57)年までの4年間に、ビデオソフト、ビデオ機器(ハード)の売り上げは20倍になるという勢いを示していたのです。82年の統計によると、ビデオ機器の売り上げ台数は1年間で520万台にのぼり、全世帯への普及率も15%に達していました。かつてテレビの普及が10%ラインを超えたところから爆発的になった経験に照らし、普及率がさらに急上昇することは目に見えていました。このまま事態を放置しておいて、旧作映画の放送やテレビ・ドラマが家庭で次々に録画されてしまったら俳優としての被害はどうなるか、考えただけでもゾッとする問題でした。
そんな中で典型的な問題として浮き彫りになったのが、NHKの連続テレビ小説「おしん」のビデオ化です。当時、人気絶頂だったテレビドラマの作家、橋田寿賀子氏の書き下ろしによる「おしん」は、奉公先で徹底的ないじめに遭いながらも耐えに耐えて生きていく少女の姿を描き出した内容が視聴者に受けて、視聴率62.9%という大変なヒットになっていました。NHKが放送した番組をレコードやビデオテープにして再利用することについては、1975(昭和50)年6月9日に芸団協とNHKで締結した「実演の再利用の報酬に関する覚書」があり、作品を管理しているNHKサービスセンターと出演者との交渉が行われるシステムが確立していました。「大河ドラマ」のビデオ化ではこのシステムによる解決が図られてきたものです。しかし、「おしん」の場合はノーカットでビデオ化されるため、録画量が多く、出演者の数も大勢になるという未経験な問題が浮き彫りになりました。
さらに、新しい問題として、舞台公演をそのまま録画撮りして商品化するという問題も生じてきました。東宝が制作した「近松心中物語」の商品化でした。未経験の問題を二つ同時に抱えた日俳連としては、当面の解決のためには、ともかくマネ協、新劇団協との協力で、製作者側との交渉を行うしか方法はありません。日俳連では「協定契約委員会」の小泉博委員長を中心に交渉団を組織、三団体との結束の下に交渉を展開して、それぞれに合意を取り付けるまで話し合いを続けたのでした。