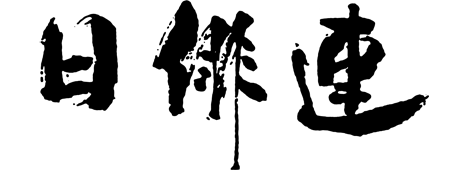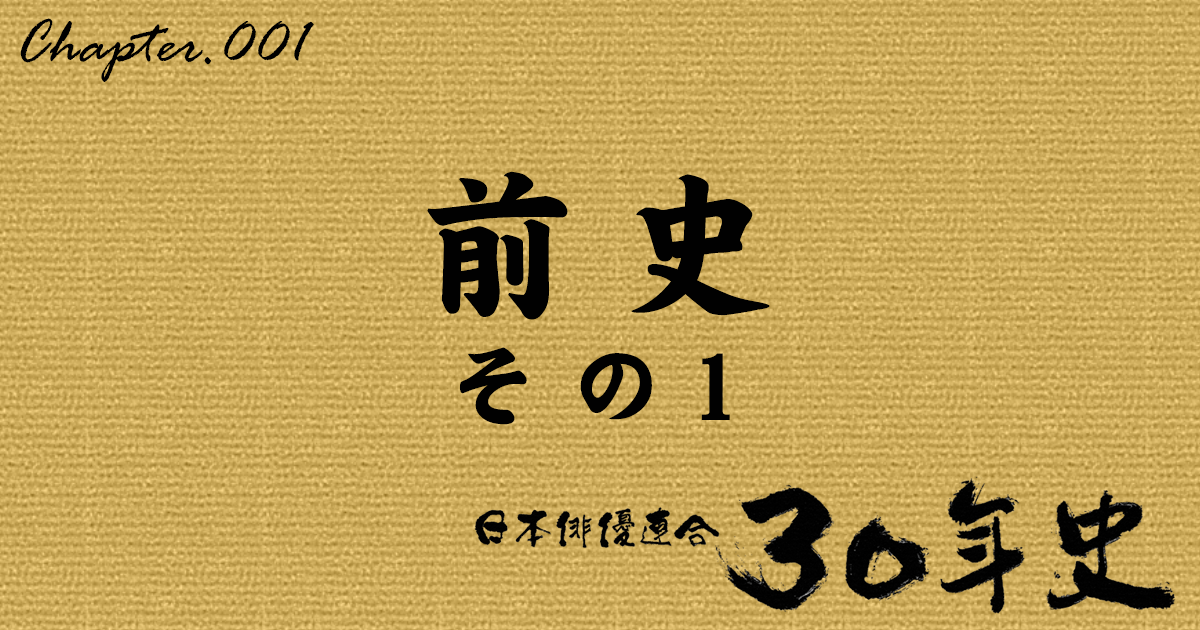-1991年- アラーム・キャンペーン
「ちゃんと考えよう出演ルールのこと」との副題の付いたこのキャンペーンは森繁久彌理事長のアイディアによるものです。「俳優はアラームにならなきゃダメだよ」の一言が日俳連の一大キャンペーンとなったのです。図で見ていただけるように、目覚まし時計をデザインしたチラシを作って組合員に渡し、出演先の楽屋などで、まだ日俳連に加入していない実演家の人々に訴えて行こうという趣向です。この考え方が一つのきっかけになって、1991(平成3)年2月26日、東京の航空会館で芸団協の主催するフォーラム「ちゃんとつくろう映画利用のルール――ないがしろにされている出演者の権利――」が開催されました。この年、4月には衛星放送「WOWOW」が放送開始となり、旧作の日本映画が次々とテレビ画面に登場するようになります。しかし、出演者には一言の断りもなく、もちろん一銭の報酬も支払われません。著作権法の映画利用に関わる例外規定をフルに利用した映画会社と放送局の態度が露骨に表面化したと言っても過言ではない状況が生まれてきたのです。芸団協主催のフォーラムは、こうした背景の打開を目指したものでした。
フォーラムの基調報告を担当した日俳連常務理事の江見俊太郎氏は、日俳連の実施したアンケートを基に
メディア技術の急速な発展に法律は後追いの状態である
俳優は映画のテレビ放送やビデオ化を認めていない
衛星放送に使われた映画の出演者はどのような意見を持っているか
について次のように語りました。
映画は太平洋戦争敗戦後の日本国民に大いなる夢と楽しみを与え、国の復興にも役立ちました。しかし、映画館が押すな押すなの大盛況であったのは昭和30年代の半ばまでです。昭和28年に始まったテレビが普及するにつれて、次第に衰退の一途を辿ります。そして、先ず、新東宝映画が昭和36年に倒産し、旧作映画550本をテレビ局に売却しました。その7年後には、各映画会社が続々と旧作を売り始めました。
科学技術の発達に対応して実演家を保護しようという「隣接権条約(ローマ条約)」が締結されたのは、皮肉にも、日本で一つの映画会社が倒産したのと同じ年です。そしてさらに注目すべきことは、ビデオが開発されたのはこの条約の採択の翌年、昭和37(1962)年なのです。つまり、この条約はビデオのことは想定せず、シネマ(劇場映画)の(利用規制)については各国の自主性に任せてしまったのです。日本もこの条約には昨年(1990年)加盟しましたが、日本での著作権法上は、俳優は映画の後の利用については、出演前の「契約」で定めておかなければならない規定(これを「ワンチャンス主義」といいます)になっているのです。
2 について
最初に映画がテレビ局に売られたとき、日本映画俳優協会(映俳協)は新東宝と交渉して150万円を受領し、その後も各映画会社に申し入れを行っています。また、著作権法の改正について、長年、継続的に要請を行い衆・参両議院でも、1986(昭和61)年以降、3回にわたって「付帯決議」が議決されています。その付帯決議とは「ビデオディスクの発達等により、録音録画された実演の利用が多様化している等の実態を勘案して、実演家の権利の適切な保護等について検討すること」という内容です。
3 について
1990(平成2)年4月から1991年1月までの10ヶ月間で、地上波放送(東京7局とTVK)で放送された旧作映画は、邦画430本、洋画911本。衛星放送(NHK)だけでも邦画112本、洋画268本にのぼった。
この中から衛星放送(NHK)で放送された作品66本を対象に64人の日俳連組合員に問うたところ、「自分の出演作品が放送されることを事前に知らなかった」人が73.5%を占め、「出演当時に劇場以外での使用に関する取り決めをした」人は0%。「出演時に劇場以外で使われることがあるとは思わなかった」人が98.4%と、いう結果でした。そして「報酬を支払って利用すべきだ」と考えている人が75%に達しています。
こうした動きに触発されたのでしょうか。この年11月には、「映画」における俳優の権利について、音議連の臨時総会(20日)と文化庁での著作権法改正をにらんでのヒアリング(22日)が行われ、音議連総会の方には日俳連から20人のメンバーが、ヒアリングには同じく日俳連から4人の代表者が出席して主張を展開しました。
方言指導懇談会の発足
ドラマの中に方言の台詞が出てくる場合、それをどのようにこなすかはなかなか難しい問題です。郷土色をより鮮明にするためには発音もイントネーションもその地域独特のものにしなければなりません。しかし、郷土色が出過ぎてしまって、その土地の出身者でなければ分からないところまでいってしまっては、かえってドラマの面白さを殺いでしまいます。とくにテレビドラマとなれば、全国の視聴者に理解して貰うことが出来て、しかも郷土色も損なわれないしゃべり方が求められることになります。
「ドラマの中の方言を考える」――をキャッチフレーズに、日俳連の中に「方言指導懇談会」が誕生したのは、テレビ、映画など映像作品の中でより効果的な方言の台詞を使うための研究が大きな目的でした。また、同時にもう一つの大きな目的として設定されたのが、方言指導をする際の指導者の待遇を確立するということでした。
「方言を教える」ことは、その土地の出身者であれば、まず、誰でも可能でしょう。言語学者であれば、もっと理想的とも言えます。
しかし、ドラマの中の台詞の扱い方となると、これは俳優でなければできないと言うことになります。演技をこなしながら、さまざまな仕草を考えながら台詞を読むとなると、そこには自ずから唯の話し言葉だけでは済まないイントネーションが必要になりますから、標準語(全国共通語)で書かれた台詞を方言に翻訳する際には、芝居が分かっていないとできないという問題が出てきます。つまり、そこには特殊な技術が必要なわけで、誰でも出来るという話ではない。また、片手間で出来るという話でもないと言うことになります。
「方言指導者の待遇を確立し、従来の片手間扱いからきちんとした職業としての扱いにして貰うためには、日俳連の中に確固とした組織を立ち上げる必要がある」――こうした考え方は、まず、関西在住の組合員の間から起こり、常務理事の国田栄弥氏から提起されました。そこで、1991(平成3)年4月26日に行われた常務会で組織作りが議題として取り上げられ、具体案提示のためにオブザーバー出席した大原穣子氏によって「方言指導懇談会」の設置が提言されたのでした。大原氏に常務会出席を進言し、常務理事に話をつないだのは嶋俊介氏であり、その後懇談会設置に向けて指導したのは常務理事の江見俊太郎氏、組織化に向けて大原氏を補佐したのは高橋ひろ子氏です。
その後、この懇談会は、代表世話人を大原穣子氏、世話人を高橋ひろ子氏、津野哲郎氏、名川貞郎氏、冨田祐一氏、江角英明氏らとして活動を広げることになります。関西地域からは国田氏に加えて鳴尾よね子氏、東海地域からは南知文子氏らが側面協力を続けました。
方言指導の担当者は、
- ドラマの台本全体を把握し
- 本直しにかかります。場合によると作家が全体をすべて標準語で書いてしまうこともありますから、全部を方言にするための調査に手間取ることもあります。
- 次に方言で台詞をしゃべったテープを作成します。キャストの役に合ったしゃべり方で実際の出演者に分かりやすいように手本を示すのです。
- そして、最後はリハーサル、ロケ、本番に立ち会います。発音の間違いを指摘するだけでなく、方言にふさわしい身振りも示す必要があるからです。これは結構な重労働だということが出来ます。
ところが、現実には、ドラマの制作現場で監督やディレクターが気安く「君は〇〇の出身だろ? ちょっとこのしゃべり方教えてやってよ」という具合に、ただ働きをさせているケースが多いのでした。
そこで「これではいけない。特殊技術にはそれに見合う報酬が確立されなければならない」との認識から立ち上がったのが、方言指導懇談会だったのです。この活動は後に「方言指導研究会」と名を変えて進められることになりますが、当初は問題点の解決を語り合うということで「懇談会」でスタートしたのでした。第1回の会合が開かれたのが1991(平成3)年5月29日。続いてほぼ1ヶ月後の7月3日には第2回目の会合を開いています。上に示したような実態を製作者に理解させ、労働の対価を正当に評価させるにはどうしたらよいか。全国で同じような仕事をする俳優をどうやって組織化し、結束するか。懇談会は、こうした問題から討議を開始しました。そして、翌92年にはNHKに対して方言指導の最低料金ならびに料金体系の確立を要求することになります。
再び声優の待遇改善を
アニメの「白味線取り」に象徴されるアニメ制作現場の劣悪な状況を改善するとともに声優の待遇悪化を如何に向上させるか。その運動は1991(平成3)年に入ると一気に燃え上がり、18年前の「出演料3.14倍獲得」と同規模の闘いが組織される勢いとなりました。この年3月12日には東京・八丁堀の勤労福祉会館での決起集会を皮切りに、800人もの参加を得たデモ行進が八丁堀 → 桜橋 → 宝町 → 鍛冶橋 → 数寄屋橋 → 土橋(銀座7丁目)の順路で行われ、最後には日航ホテルでの記者会見となるのですが、この準備はなんと正月の松も開けやらぬ1月6日から進められたのでした。この日、事務局に集まって委員会を開催した外画動画部会は、自分たちを取り巻く情勢分析をし、再びデモや出演拒否に訴えるかどうかを検討します。
ただ、この日には結論を出せずにいた俳優に強く勇気を与えてくれたのは、やはり、森繁理事長でした。 ギャラ体系の現状の説明を聞いて「そんなに安くちゃいけないよ君達!!」と叱正する森繁理事長の言葉に励まされた外画動画部会は、1月13日に東京・神宮外苑の日本青年館に212人を集めて部会総会を開催、意思統一を図った結果、1月22日に「アニメを支える会準備会」を発足、24日にはデモに向けての広報企画部を結成するというように着々と準備を進めるのでした。
デモ実施の3月12日は晴れでした。その前の9日から降り始めた雨は10日も、11日も降り続き、委員たちをやきもきさせましたが、当日朝になって心地よい晴天。決起集会を開いた勤労福祉会館には入りきれないほどの声優と支援団体の人々が集まりました。
「アニメは子供の夢 こわすな子供の夢」
「子供達の文化を守ろうアニメーション」
「ジュニア制度は賃金あげない悪だくみ」
「聞いてびっくりアニメ予算と役者のギャラ」
など、いくつものプラカードがデモ行進の中に林立し、町行く人々を驚かせたものです。
そして記者会見。銀座7丁目の日航ホテル・コンドルルームには二谷英明専務理事、江見俊太郎常務理事、大平透理事、矢田稔理事らが揃い、アニメの製作現場におけるさまざまな矛盾点、声優の待遇の悪さを訴えました。当日、外画動画部会委員としてこの会見を見守っていた野沢雅子氏によると、訴える側の勢いが良すぎて記者団はメモを取るのに精一杯。質問を発することもなく、早々と引き上げていったとのことでした。
この一連の行動は、やがて、日俳連、音声連、マネ協の三者による「合意書」となって結実します。1991(平成3)年7月17日、調印された内容は
- 最低ランクを1万5000円とし、日俳連の組合員であるなしにかかわらず、これ以下で出演してもさせてもならない。
- すでにランクを持っている人は、段階によって順次引き上げ、日俳連の目標であるランク1.5倍引き上げを、平成4(1992)年4月1日実施目標に行う。
- ランクの上限は4万5000円とし、それ以上をノーランクとする。
- 時間割り増し、ビデオ化に関しては新しい料率を設定する。
となりました。これによって声優の出演料は平均1.7倍の増額を獲得することが出来たのです。目標であった平均2倍の増額獲得には達しませんでしたが、闘いの成果はそれなりにあげることの出来た取り組みでした。
映像3団体 共同の「災害防止提言」
1988年(昭和63)年7月に起きた「軽井沢シンドローム」撮影中の自動車事故、同年12月の「座頭市」立ち回り中の真剣による死亡事故、さらに1989(平成元)年2月のにっかつ撮影所での火災と相次いだ大事故を教訓に「映像製作現場の労働災害を防止するために」という提言が映像三団体連絡会の統一提言としてまとめられ、1991(平成3)年3月28日、労働省、文化庁、NHK、民放連、全日本テレビ番組製作者連盟(ATP)に、翌3月29日には映連に、4月12日には通産省(現・経済産業省)、郵政省(現・総務省)、日本テレビコマーシャル制作者連盟(Jac)、映像文化製作者連盟に提出されました。
日本映画監督協会会長で映職連(日本映像職能連合)の会長をも務めておられた大島渚氏は、新聞のインタビューに応えて「プロデューサーたちの意識を改革しなければ、安全や質の向上のための抜本的改善はあり得ない。日本のプロデューサーは、監督や俳優を安く使うことが第一と考えている。しかし、信頼しあえるスタッフに高い報酬を支払うことを喜ぶべきではないか。製作費はかさんでも、それを回収できる作品をつくればいいのであって、いまの日本は問題が逆転している」(1991年4月24日付け、東京新聞夕刊)と述べておられますが、まさに芸能界の実態はこの通りだったのです。
三団体による提言は、こうした実態を踏まえて
- 製作費の予算の中に安全対策費を別枠で(上積みして)計上する。
- 安全対策に必要な器具器材を調達し、人員を配置する。
- 撮影・照明などの器材の安全性を点検、確認する。
- スケジュール作成に当たっては8時間労働を原則とし、最低週1回の完全休日を守る。
- 撮影(収録)作業は15時間以内にし、撮影(収録)終了後、最低10時間の休止時間をおく。とくに深夜および徹夜の後には危険な撮影(収録)は行わない。
- 危険を伴う撮影(収録)作業に俳優が出演する場合、製作会社と俳優プロダクションは、当該俳優の当日掛け持ち出演のないよう、また前日の仕事が10時間前に終了するよう調整する。
- 作品ごとに、現場における安全基準を監督およびスタッフ、俳優の間で確認する。
の7項目を提示したのでした。
ところが、こうした提言を各方面に提出した半年後、またまた痛々しい死亡事故が発生しました。1991(平成3)年9月2日、ディレクターズカンパニー製作の映画「東方見聞録」が静岡県下でロケ撮影中、重さ8kgの鎧をまとった武者姿で深さ2m余の人口滝壺に入った俳優、林健太郎氏が水を吸った鎧の重みで水没、あわてて救助され、救急車で病院に運ばれたものの死亡してしまったというものです。林氏は21歳の若さでした。
森繁理事長に文化勲章
1991(平成3)年11月3日、森繁久彌理事長に文化勲章が授与されました。芸能部門では歌舞伎など伝統芸能には贈られてきた文化勲章ですが、現代劇俳優としての受章は初めての快挙です。