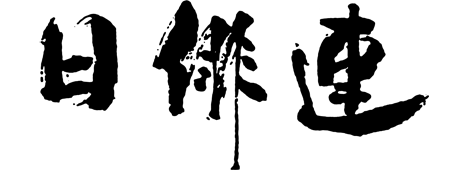新著作権法制定へ
1899(明治32)年の発布以来、70年振りとなる著作権法の改正案が、1969(昭和44)年4月18日、国会に上程されました。時代の変化、技術の進歩、1964(昭和39)年の「実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(ローマ条約)」の発効による国際的な流れ、それに芸能実演家からの強い要請などを映しての上程でしたが、法案の中身には大変な問題点が含まれていました。
新しい著作権法の最大の特徴は「著作隣接権」という新しい概念を持ち込んだことでした。俳優や演奏家、演芸家など実演を 業 とする者は、小説家、劇作家、作曲家などとは違って著作を行う者ではありません。従って、著作者、著作権者ではあり得ない。しかし、他の人の著作物を具現化した演技や演奏、口述で観衆、聴衆を魅了する創意や技術を擁しています。そこで、こうした実演家には著作隣接権という新しい権利を与えて、法律的にも保護しようという考え方が持ち込まれたのでした。
これによって実演家には新たに3つの権利が保障されることになりました。すなわち、
- 実演をすることと、その実演の利用を許す権利(実演権)
- 実演を録音したり、録画したりすることを許す権利(録音権および録画権)
- 実演を放送することを許す権利(放送権および有線放送権、これに1997年以降は「映画」だけは例外とするが、生の実演をインターネットなどにアップロードすることを許す権利「送信可能化権」が加えられます)
です。
さらに、権利が確立したことによって、商業用レコードの二次使用に関する規定が政令で定められるようにもなりました。
しかし、著作隣接権にはいくつかの大きな問題点がありました。
一つは、同じ著作隣接権者の中に「実演家」と並列してNHK、民放テレビ局などの「放送業者」、さらには「レコード製作業者」が一緒くたにされてしまったことです。放送業者もレコード製作者も他の著作者が創造したものを伝達する役割を負っている、だから著作権者ではなく隣接権者だ、という論理です。でも、誰でもが知っているように、放送局やレコード会社は大きな資本に裏打ちされた巨大企業であって、個人で仕事をしている実演家とはまったく違います。また、放送局は自らの力でドラマなどを製作しますから映画会社のように著作権者になり得る能力を備えています。このように誰が考えても分かる力の差のあるものを同じ著作隣接権の概念の下に並列してしまったのが大きな問題点でした。
そして、もう一つは、映画の著作物の利用に関して、例外的に実演家の権利を大きく制限してしまったことです。さらに、三つ目として著作者の「人格権」((1)自分の作った未公表著作物の公表の可否を決定する権利としての「公表権」、(2)自分が作ったと名前を表示する権利としての「氏名表示権」、(3)自分の作ったものを勝手に改変するなと主張する権利としての「同一性保持権」の三つで成り立っています)を規定しながら、著作隣接権者には一切人格権を認めなかったことも大きな問題でした。これによって、映画がどのように二次利用、三次利用されても、俳優にはなんの金銭的利益ももたらされなかったばかりか、映画の一部を改変して利用して出演している俳優の名誉・声望が傷つけられてもそれを回復する方法すら認められないことになってしまったのです。
これらの問題点は、やがて悪い方に援用され、放送局がその関連会社に発注して製作させた放送番組用の作品までが「テレビ映画」の名の下に、俳優の権利が届かない「映画」の範疇に入れられてしまいます。それによって、俳優が受けてきた被害がどれほどであったか。それを食い止めるために、いかに心血を注ぎ込むことになるか。それは、放芸協から日俳連に移行し発展して行く過程で、常に、俳優たちが抱える大きな大きな課題でした。
しかし、大きな問題点を抱えた新著作権法は、1969(昭和44)年8月には一旦審議未了となったものの、翌70年(昭和45)年2月には、再びまったく同じ内容で上程され、同年4月10日に衆議院全員一致で可決、同月28日には参議院で賛成多数を得て成立し、翌1971(昭和46)年1月1日には発効の運びとなったのです。
新著作権法の抱える問題点を実演家たちがただ呆然と見過ごしていたわけではありません。芸団協は国会に強く働きかけ、衆議院の文教委員会に参考人として紙恭輔常任理事(久松保夫常任理事が随行)を送り込むなどして、法案の修正を求めました。しかし、国会の壁は厚く、修正は認められませんでした。ただ、こうした努力の結果は、衆・参両議院文教委員会による付帯決議として残りました。その要点を示しますと
- 法の運用に当たっては、著作物の公正な利用についてのよい慣行が育成されるよう著作権思想の普及に努力すること。
- 著作物の利用手段の開発は急速なので、時宜を失することなく、次の制度改正に向かって検討を始めること。
などです。
しかし、この決議が具体化される動きは、実態として、生じませんでした。
以後30数年にわたって、俳優は苦難の道を歩まされることになります。そもそもの元凶はどこにあったのでしょうか。新著作権法が、その立案に当たって、ローマ条約を下敷きにしたところが問題だったとも言えるでしょう。それが証拠に、WIPO(世界知的所有権機関)でも、その後30年にわたってローマ条約に替わる国際条約の採択に向けた努力が続くことになります。
映画を中心に、映像文化の発展とその中での実演家の権利の確保、それこそが放芸協、日俳連を通じた30数年の歴史の命題であった、と言っても過言ではありません。
マネージャー協会の設立
1969(昭和44)年から1970(昭和45)年にかけては、このほかにも放芸協、日俳連の歴史を語る中で記憶に止めておくべき事象が起きています。
例えば、製作プロダクションの倒産に伴う出演料の未払い問題、放送番組がビデオになって市販されるVCR=ビデオ・カートリッジ・レコーダー=の出現、そして芸能マネージメント協会の設立などです。これらの動きは、やがて、芸能家総連合の構想を生み出し、現実には「日本俳優連合」の設立へとつながっていきます。
製作プロの倒産と出演料未払いの問題は、1969(昭和44)年4月に表面化しました。日本テレビ・吉永プロ制作のテレビ映画「風の中を行く」の実際の制作を請け負っていた銀座プロダクションが資金繰り悪化から倒産し、出演していた俳優への支払い分1,250万円もの巨額が未払いになってしまったのでした。
VCRは、一言で簡単に言ってしまえば、小型カセット式のテープを使う簡易レコーダーのことです。こんな機械が開発発売されるようになったため、TBSから一気に50本ものドラマがテープになって発売されたり、東宝の映画がソニーから発売されるという騒ぎになったりしました。しかし、問題はそれだけに止まりません。録音用の機械が発売されることによって視聴者が家庭で勝手に番組を録画する心配も出てきたのです。
マネージャーが結束して一つの連帯組織を結成しようと動き出したのは、こうした情勢下でした。実演家のマネージメントを生業としているマネージャーも、ただそれだけの仕事をこなすのではなく、急速に変化していく社会情勢を的確に把握し、連帯から生まれる力を利用して権利の拡大に寄与しようと考えたからでした。1970(昭和45)年4月16日、芸団協にマネージメント事務所を代表する31人が集まって準備会を開くと、5月9日には東京銀座の電通ビル8階ホールで、早くも結成総会を開催する運びになり、「芸能マネージャー協議会」として設立されました。これが、現在の「日本芸能マネージメント事業者協会」の前身です。
一方、実演そのものを生業とする俳優の間では、さらに大きなスケールによる連合組織の結成が考えられていました。いわゆる「芸能家総連合構想」でした。
1965(昭和40)年に発足した全ての芸能実演家を包含する団体協議会「芸団協」には、その後、活動をより組織化し、強化するための組織委員会(委員長・片谷大陸氏、副委員長・江見俊太郎氏、ほかに委員として放芸協理事の浮田左武郎氏)が設置されていました。俳優、音楽、舞踊、演芸の各部門から選ばれた組織委員は慎重な研究を重ねていましたが、分かったことは芸能界ではどの分野においても共通の悩みと要求を抱えていること、しかもどの分野でも個々の団体では容易に問題解決に至らないことでした。また、芸団協は芸能界の全ての団体を包含する組織ですが、社団法人という公益のために尽くすことを第一義にしている以上、各個人の利益を守ることを主たる目的にすることは困難だということも分かってきました。
そこで、出演条件等で共通の悩みを抱えている4つのジャンルの団体が集まり、連合としての力の結集を図ろうとしたのが芸能家総連合構想だったのです。4つのジャンルとは
- 俳優連合(演劇、映画、放送、能楽、文楽等)
- 音楽家連合(演奏家、歌唱者、指揮者等)
- )舞踊家連合(邦舞、洋舞)
- 演芸家連合(講談、落語、浪曲、漫才、奇術、曲芸等)
でした。そして、この4つの連合が有機的に結集し、1971(昭和46)1月から発効する新著作権法の精神を生かして製作会社、放送局との間での基本協約を作成していこうではないか、と考えたのです。また、芸能実演家の所得税に関する基礎控除額の引き上げなど税務対策、外国の芸能実演家組織との交流による情報の収集なども視野に入れていました。さらに、諸外国のユニオンとの提携も実現して、日本にやってきた外国のタレントが野放しで日本のメディアに出演するのを規制していこうとも考えていました。
ジャンボ機内の外国映画問題解決
さらにもう一つ特記しておきましょう。それは1970(昭和45)年7月1日から就航した日本航空ボーイング747ジャンボ機内で上映する外国映画日本語版の収録に関する出演条件が整備されたことです。問題提起は、この年の5月に結成された芸能マネージャー協会からされました。飛行機内の映画上映は、いわば動く劇場映画館のようなもので茶の間のテレビ映画鑑賞とは異質であること、折しも新しく著作権法が発効しようとしているタイミングでもあり、いい加減な対応をすると実演家のその後の録音権行使に大きな影響を与えかねないという意識も働いていました。
話し合いは、発注元の電通(機内上映の機器とフィルムについて権利を持つアメリカのインフライトモーションピクチャーの日本代理店)、放芸協、芸能マネージャー協議会、新劇団協議会の4者間で行われましたが、結局
- 日本語版の利用範囲は航空機内の上映に限る
- 出演料は、各出演者の30分の基準出演料の100%相当額を最低とする
- 覚書は当面の暫定措置として取り交わす
ことで合意しました。
関西俳優協議会の結成
1970(昭和45)年11月5日、関西地域在住の俳優が、フリーグループを含めて16団体、377人を組織して「関西俳優協議会(略称・関俳協)」を発足させました。東京では放芸協が結成され、事業協同組合として法人格を取得する。また、芸能実演家を総合する形で芸団協が組織されるという中で、「関西もきちんとした組織を持たなあかん」というわけで、舞台、映画で活躍中の毛利菊枝さんを中心に結束しようとしたものでした。
俳優としての出演条件、待遇がメディアの発達とともに悪化していく状況については、東京での事情を中心に、これまで説明してきたとおりですが、仕事量の少ないことなど条件の悪さはむしろ関西をはじめとした地方の方が深刻だったと言えるでしょう。また、新人の俳優を育成してゆく機関やチャンスも地方へ行くほど恵まれないものになってきます。こうした事態に正面から向き合い、自ら解決できるものには自らの力で対処する。それが関俳協の意気込みでした。
初代の会長には毛利菊枝さんが就任。その後、海老江寛氏、西山辰夫氏、国田栄弥氏、田中弘史氏と会長が引き継がれます。
翌71年9月には、設立されたばかりの日俳連から江見俊太郎理事(組織担当)、村瀬正彦事務局長が大阪を訪れ、関俳協の委員会に出席して日俳連への加盟をPRしました。俳優の組織は大きければ大きいほどいい。是非、日俳連に結集を、というわけですが、両方に入れば会費は二重になるのか、関西独自の問題解決にどれだけ力が割けるのか、など疑問も提示されました。
この問題は、その後、30年を過ぎても残されている課題です。